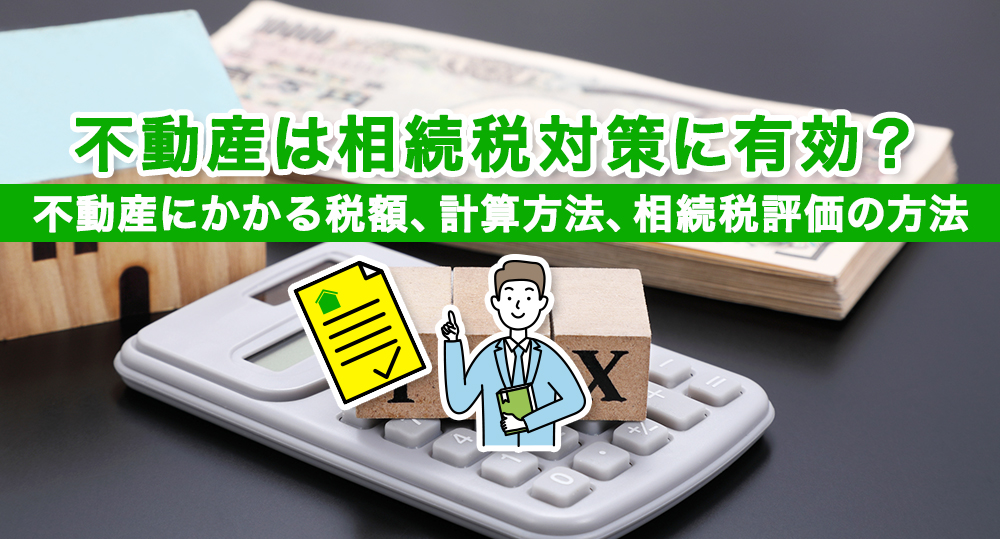
まとまった資産を相続すると、相続税が発生します。相続税には基礎控除がありますが、資産の合計額がそれらをはるかに上回れば、相続税も大きくなります。相続税を節税するには資産を不動産で保有するのが有効とも言われます。それはなぜなのでしょうか。
ここでは、相続した不動産にどれほど課税されるのか、その計算方法や、相続した不動産の評価方法について解説します。

不動産はなぜ相続税対策に有利なのか
被相続人が亡くなると、被相続人の保有していた金銭的に見積もることのできるすべての資産が課税対象となります。その際、不動産は現金など流動資産で保有しているよりは、相続税対策に有利と言われます。それはなぜなのでしょうか。ここではその理由について、解説します。
現金・金融資産は時価100%

現金・預貯金・株式・公社債などは流動資産と呼ばれ、原則として時価の100%が相続税評価額となります。とくに現金の場合は、何年たっても1万円札は1万円の価値を持ちます。預貯金は相続開始の日の預入残高と相続開始の日に解約するとした場合に支払いを受けられる既経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差し引いた金額)との合計額が相続時の評価額になります。
上場株式は相続発生時の終値かその月あるいは前月、前々月の終値の平均額の一番低い額を選べます。
取引相場のない株式・出資については、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などを用いて評価します。このほか、債券は満期までの日数に応じた調整が行われますが、これらの流動資産は、時価の100%に対して課税されます。
不動産には特別な計算方法がある
一方、不動産は現金などと違い、換金しなければ相続税を払えません。換金するのに一定の労力が必要となるので、評価額は現金などのように時価100%ではなく、時価よりも低く評価されます。また、不動産の価格は一定ではなく常に変動しているので、正確な時価を把握するのは難しくなります。
そこで、国税庁では、土地の相続税には路線価方式と倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額に基づいて評価しています。
時価100%の現金に比べて、時価より低く評価される不動産の場合、その差分が相続税の節約になるので、上手に不動産を活用すれば節税が可能になります。
例えば、遺産が8,000万円とした場合、すべて現金であれば、相続財産の評価額は8,000万円で、8,000万円に対して相続税が課税されます。しかし、遺産がすべて不動産の場合、相続税評価額が5,000万円と評価されると、現金に比べて評価額は3,000万円の減額になります。
不動産の相続税評価額の計算方法
不動産の相続税を計算する場合、納税者が自分で土地・建物の時価を把握するのは容易ではないので、国税局では、相続税等の申告の便宜と課税の公平を図る観点から、毎年全国の民有地について、土地の評価額の基準となる路線価と評価倍率を定めて公開しています。建物の場合は固定資産税評価額が用いられます。
また、居住用の小規模な土地などに対して相続税評価額を減額できる小規模宅地等の特例があります。
以下では、土地の路線価方式と倍率方式、建物の場合の固定資産税評価額、小規模宅地等の特例について解説します。
土地部分の相続税評価額
土地の相続税評価方法には、市街地などで使われる路線価方式と郊外や農村地などで使われる倍率方式があります。評価時点は毎年1月1日ですが、1年間の地価変動などを考慮して、公示地価の80%程度を目安に定められます。
路線価方式
毎年各国税局が作成する路線価図にもとづいて土地を評価します。ほとんどの市街地で適用されています。路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
路線価方式による土地の評価額の計算は、路線価を土地の形状に応じた奥行価格補正率など各種の補正率で補正した後、その土地の面積をかけて算出します。計算式は以下のようになります。
評価額=路線価 ×補正率・加算率 × 地積
この場合の補正率と加算率は奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率のことで、路線価図に示された地区等に応じた率が決められています。
奥行価格補正率とは、土地が接している道路からの奥行きが深すぎたり浅すぎたりするとその土地が使いにくくなるため、その分土地の評価額を減額できるように乗じる割合のことです。
側方路線影響加算率とは、正面と側方に路線がある宅地を評価する場合、側方路線に接していることが宅地の価値に影響を与えるので、正面路線のみに接する場合の価額に一定額を加算するために、側方路線の路線価に乗じる割合のことです。
二方路線影響加算率とは、正面と裏面の両方で道路に接している土地を評価する場合に使われます。正面と裏面で道路に接していれば、両方の道路から出入りができ、利便性がアップすると考えられるので、相続税の財産評価では、利便性のアップを反映させるために二方路線影響加算率で評価額を修正します。
例えば、路線価図では1㎡当たり千円単位の数字が載せられています。100とあれば、1㎡当たり10万円です。土地の広さが150㎡であれば評価額は10万円×150㎡=1,500万円になります。もし、奥行きが4m未満の普通住宅地区の場合の奥行価格補正率は0.9となるので、奥行き補正を加えた土地の評価額は1,500万円×0.9=1,350万円となります。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域における評価方式です。郊外や農村部では倍率方式が用いられます。土地の評価額はその土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。この場合の一定の倍率は地価事情が類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額や公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格などをもとに、国税局長が定めます。固定資産税評価額は都税事務所、市町村役場で確認できます。計算式は以下のようになります。
評価額=固定資産税評価額 × 倍率
例えば、固定資産税評価額が2,000万円、倍率1.1倍の宅地の評価額は2,000万円×1.1=2,200万円となります。
小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業に使われていた宅地や居住用の土地等のうち一定のものがある場合、その宅地の一定の面積まで、区分に応じて50%~80%が減額できます。
330㎡までの部分について80%減額
被相続人等の居住用として使われていた宅地等の場合(特定居住用宅地等)は、面積が330㎡を限度として80%が減額されます。適用要件は、相続人が被相続人の配偶者であれば問題なく適用できます。
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が取得した場合は、相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつその宅地等を有していることなどが必要です。
また、被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等の場合は、取得者が相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで有していることが要件となります。
400㎡までの部分について80%減額
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等)以外の事業用の宅地等(特定事業用宅地等)、あるいは貸付事業用の宅地等で一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等(特定同族会社事業用宅地等)に該当する宅地等の場合、面積が400㎡を限度に80%が減額されます。
要件は、特定事業用宅地等の場合は、被相続人の事業の用に供されていた宅地等の場合、取得者が被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぐとともにその申告期限までその事業を営んでいることが必要です。被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等の場合は、取得者が相続開始直前から相続税の申告期限までその宅地等の上で事業を営んでいることが必要です。いずれもその宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件となります。
特定同族会社事業用宅地等の場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等を除く)の用に供されていた宅地等で、取得者が相続税の申告期限にその法人の役員であり、申告期限までにその宅地を保有していることが要件となります。
200㎡までの部分について50%減額
被相続人等の事業に使われていた宅地等で、一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等やその法人の貸付事業用の宅地等、また被相続人等の貸付事業用の宅地等(これらを貸付事業用宅地等という)は、面積200㎡を限度に50%が減額されます。
このうち被相続人の貸付事業に使われていた宅地等の場合、取得者がその宅地等に関する被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていて、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが要件となります。
また、被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等の場合は、取得者が相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等に係る貸付事業を行っていて、その宅地等を申告期限まで有していることが要件となります。
私道

私道には、公共の用に供する、不特定多数のものが通行する通り抜け道路と、そうでない特定のものが通行する行き止まり道路があります。公共の用に供する私道は相続税の対象とはなりません。特定の者が利用する私道は、路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30%相当額になります。
つまり、路線価方式あるいは倍率方式で評価した価額に0.3をかけることによって、私道の評価額が計算されます。所有者専用道路の場合は宅地の一部となるため、宅地とともに評価します。
建物部分の相続税評価額
建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。建物とは、住家、店舗、工場、倉庫などで、ガスタンクや機械上の建造物などは建物として扱われません。建物の固定資産税評価額は再建築価格方式が採用されています。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことです。評価額は再建築価格に対して建築からの経年数に応じた減価を経年減点補正率(家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率)等によって計算します。
賃貸不動産はさらに評価額が下がる

アパートなどが建っている土地、すなわち貸家建付地の相続税評価額は、通常の宅地に比べて低くなります。これは賃貸不動産の場合、所有者が自由に使えないという判断がされるからです。賃貸借契約では借主様の権利すなわち借家権が守られるため、簡単に契約を解除できません。賃貸不動産の所有者がその不動産を自由に使うには大きな制約があるためです。
一般の宅地などは自用地と言いますが、貸家建付地の価額は、その宅地の自用地としての価額に対して、その宅地の借地権割合とその貸家に係る借家権割合によって評価額が変わります。
土地部分(貸家建付地)の相続税評価額
賃貸不動産の土地部分である貸家建付地の相続税評価額は、以下の計算式で評価されます。
貸家建付地の評価額=自用地としての評価額×(1-借家権割合×借地権割合×賃貸割合)
数式のうち「借家権割合」は、賃貸者人が住む土地や建物は転用しにくいことから、自用地あるいは更地と同じ評価ができず、借家権割合は全国一律30%の評価減が適用されます。
「借地権割合」は、路線価に下記のようなアルファベットの記号で示されています。貸家建付地は借地権割合に応じて減額されます。
A:90% B:80% C:70% ・D:60% ・E:50% ・F:40% ・G:30% ・空欄:20%
「賃貸割合」は、満室時の専有面積を100%として、貸付している部屋の面積の割合になります。例えば、延床面積が312㎡(1部屋20㎡で16部屋)のアパートで2部屋が空いている場合、つまり14部屋が使用されていれば、賃貸割合は20㎡×14部屋÷312㎡=89.7%となります。
すなわち、借地権割合が低いほど、また賃貸割合が小さい(空室が多い)ほど、土地の相続税評価額は上がります。
例えば、自用地の評価額が8,000万円、借地権割合が60%、賃貸割合が80%の場合、借家権割合は30%なので、貸家建付地の評価額は以下のようになります。
貸家建付地の価額=8,000万円×(1-0.3×0.6×0.8)=6,848万円
※空室が「一時的な空室」と認められれば賃貸割合100%とすることができます。
建物部分の相続税評価額
一方、賃貸不動産の建物部分は以下の計算式で評価されます。
貸家建付地の建物の相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
相続発生時に貸している部屋が少ないほど、相続税評価額は上がります。
まとめ

不動産の相続税評価額は現金のように時価100%にならず、独特の計算方法があります。基本的に不動産の相続税評価額は時価よりも低く評価されるので、相続税額はその分少なくなります。賃貸不動産であれば、賃貸部分をさらに控除できるので、相続税をさらに減額できます。
こうした特性を利用して、相続される土地にアパートを建てるなどの節税対策が行われます。しかし、所有している財産で不動産の割合を多くした場合、遺産分割でもめやすくなることや不動産市況が冷え込んで時価が下落することもあるので、注意が必要です。
節税対策には専門的な知識は欠かせません。相続に関しては見識のある、信頼できる不動産仲介会社に相談することが重要です。不動産一括査定サイトのすまいValueは不動産大手6社が運営しているので、信頼できます。不動産の相続にもすまいValueの活用をおすすめします

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください


























