
土地やマイホームなど不動産を所有している人が毎年支払うことになるのが固定資産税です。固定資産税はいつ支払うのか、どのように払ったらいいのか、初めての固定資産税に戸惑っている方に向けて、固定資産税を支払うタイミングや納付方法をお伝えします。クレジットカード払いやスマートフォン決済など、現金以外で納付する方法についても解説しています。

固定資産税はいつ納付するのか
固定資産税は不動産(土地・建物)など固定資産に対して課される税金です。まず、固定資産税の通知はいつ届き、いつまでに納付しなければならないのかについて解説します。
納税通知書が届く

税金には国税と地方税があり、固定資産税は地方税です。国税は日本政府が徴収する税金です。これには所得税、法人税、消費税などが含まれます。これらの税金は全国一律の税率で徴収され、国の財政を支える重要な収入源となっています。
地方税は都道府県や市町村などの地方公共団体が徴収する税金です。地方税には、住民税や固定資産税、軽自動車税などがあります。これらは地方公共団体の財政を支え、地域の公共サービスやインフラ整備などに使われます。
固定資産税は地方税の一つです。税収はその地域の公共サービスやインフラ整備に使われています。
固定資産税が課されるのは、毎年1月1日の時点で、その不動産の所有者として固定資産税台帳に所有者として登録されている人(固定資産税台帳とは市町村が作成する帳簿で、課税対象となる土地、家屋等について、その所在や所有者、評価額などを登録しています)。
つまり、その年の1月1日時点で物件を保有している人です。1月2日以降に物件を手放した場合も、その年の分は1月1日の時点での所有者が全額支払わなければなりません。
そこで、多くの売買契約では、固定資産税は1年間の納税額から日割りで所有権移転後の期間分の税額を計算し、買主様が売主様に清算金として支払うことが一般的です。ただし、契約内容によって変わってくるので、不動産仲介会社に確認することが必要です。
固定資産税の納税額は、固定資産税評価額×税率(標準は1.4%)です。ただし、固定資産税には軽減措置があります。
新築住宅の軽減措置
2024年3月31日までに新築された戸建てやマンションには、固定資産税が半額になる軽減措置があります。戸建ては3年間、マンションは5年間この減額が適用されます。
住宅用地の特例
住宅用として使われる小規模な土地には、税率が下がる特例があります。200平方メートル以下の土地は土地評価額の6分の1、それを超える部分は3分の1に減免されます。
省エネ改修促進税制
省エネリフォームを行った物件は、120平方メートルまで固定資産税が3分の1になります。この減税はリフォーム後の翌年1年間だけ適用されます。
バリアフリー改修促進税制
バリアフリー改修を行った場合、固定資産税が100平方メートルまで3分の1に減額されます。これもリフォーム後の翌年1年間のみ適用です。
耐震改修促進税制
耐震リフォームを行った場合、最大2年間固定資産税が半額になります。
長期優良住宅化リフォーム
耐震や省エネ改修を行い、長期優良住宅として認定されると、翌年1年間固定資産税が3分の2になります。
固定資産税の軽減措置を利用するためには、自分で申告手続きを行う必要があります(申告の期限は翌年の1月31日)。自分の場合は軽減措置が適用になるかは、税理士や納付窓口で相談しましょう。
支払方法は年4回の分割方式
固定資産税の納付は市町村から郵便で送られてくる「納付通知書」を利用します。
固定資産税は国税ではなく、市町村(東京23区内は東京都)に支払う地方税であるため、地域によって納付時期などには多少のバラツキがあります。
いつまでに納税しなければいけないのか、具体的な納税スケジュールは自治体によって異なりますが、自治体から納税通知書が送付されてくる時期は4~6月頃が多いようです。
自治体から送られてくる納税通知書には、納付する税額と支払期限などが記載されています。納付額の元となる評価額や課税標準額などの書かれた課税明細書も同封されているので内容に誤りがないかチェックしましょう。
固定資産税の支払いは、一括または年4回の分割方式が一般的です。封筒には一括用の用紙と分割用の用紙が同封されているので、慌てて5枚全部で支払わないよう注意しましょう。
分割の場合、6月・9月・12月・2月の年4期で、それぞれの期ごとに納付期限が設けられています。一括でも分割でも支払額は変わりません(一括支払いによる割引や、分割手数料などはありません)。
固定資産税を延滞すると

固定資産税は記載された期限までに必ず納付しましょう。もし支払いが遅れてしまった場合には、延滞金が発生してしまいます。
延滞金は最大で年14.6%と高利であるため、万が一、滞納してしまった場合はすぐに支払うか、自治体の窓口に相談することをおすすめします。
催告されたにもかかわらず不払いを続けると、財産や給料などを差し押さえられてしまう可能性もあります。
固定資産税の納付方法
固定資産税は現金や口座引き落としの納付が一般的ですが、2023年4月からは「地方税お支払サイト」を利用してさまざまな決済方法で支払うことができるようになりました。
現金による納付
固定資産税の最も一般的な納付方法は、現金での支払いです。現金での納付は、銀行などの金融機関のほか、自治体の税事務所の窓口(東京23区は都税事務所)、コンビニエンスストアなどに、納付通知書を持参して現金を支払います。
手数料がかからないうえ、領収証書が発行されるのがメリットです。領収書は納税証明書の発行に必要となるので保管しておくことをおすすめします。
コンビニエンスストアでの支払いはバーコードがついた納付書に限られ、1枚あたり30万円と上限額が定められています。納付書の期限が過ぎてしまった場合、納付は可能ですが、コンビニエンスストアでは支払えなくなります。
多くの自治体では銀行口座からの自動引き落としもできます。固定資産税は毎年のことなので、一度銀行口座を登録してしまえば翌年から支払いを省力化することができます。その場合でも、念のため、納税通知書と引き落とし金額の確認は忘れないようにしましょう。
現金以外の納付方法・地方税お支払サイト
最近ではキャッシュレス時代に対応して、固定資産税もさまざまな方法で納付が可能になりました。
なかでも2023年4月からスタートした「地方税お支払サイト」は、日本全国ほぼすべての自治体が加入しているサービスです。
納付書に印刷された地方税統一QRコード(eL-QRエル キュ-ア-ル)やeL番号を利用して、スマートフォンやパソコンで納税することできます。
多彩な納付方法
地方税お支払サイトは、さまざまな決済方法が利用できるのがメリットです。各種クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)、Pay-easy(ペイジー)、スマートフォン決済アプリでの支払いができます。
また、手元にある納付書が納付済みかどうかも、同サイトで調べることができます。
固定資産税以外の税金の納付も可能
地方税お支払サイトは自動車税種別割、不動産取得税、個人事業税など固定資産税以外の地方税の支払いもできます。
多くのスマートフォン決済アプリに対応
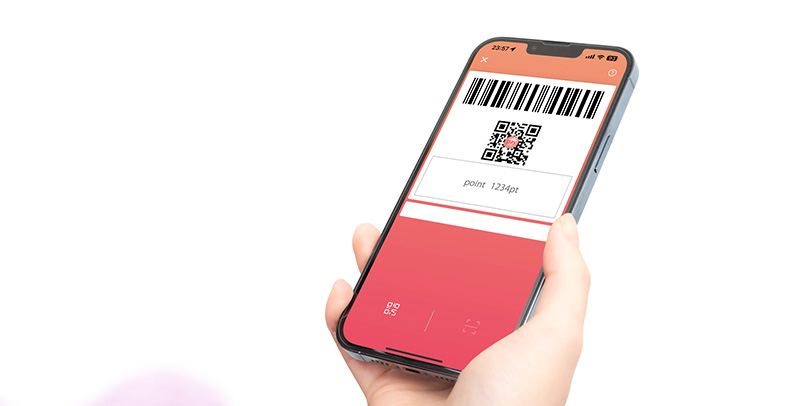
地方税お支払サイトは、多くのスマートフォン決済アプリでの支払いに対応しています。2023年11月17日時点では以下のアプリが利用可能となっています。普段利用している決済アプリがないかチェックしてみましょう。
- au PAY
- F-REGI 公金支払い
- さるぼぼコイン
- ファミペイ
- PayB
- モバイルレジ
- atone
- PayPay
- 楽天銀行アプリ
- Wallet+
- 京銀アプリ
- 北陸銀行ポータルアプリ
- YOKA!Pay(熊本銀行)
- YOKA!Pay(十八親和銀行)
- YOKA!Pay(福岡銀行)
- どうぎんアプリ
- はまPay
- d払い
- 楽天ペイ
- Bank Pay
- 真庭市地域通貨 まにこいん
- J-Coin Pay
- 西日本シティ銀行アプリ
固定資産税をクレジットカード・スマートフォン決済で納付するメリット・デメリット
固定資産税を現金ではなく、クレジットカードやスマートフォン決済で支払うと、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
メリット① 自宅で支払いができる
「外出したついでに支払おう」と思っていても、納付書を家に置き忘れていたり、持ち歩いていても出先で納付を忘れてしまったり…なんてことはありませんか?
現金で納付する場合はわざわざ出かけなければなりませんし、現金を用意する手間がかかります。窓口で支払う場合は、金融機関の営業時間に合わせなければ支払うことができません。
固定資産税をクレジットカード払いやスマートフォン決済で納付する場合、金融機関やコンビニなどに出向かなくても、インターネット経由で、いつでもどこでも支払いが可能です。
24時間自宅で決済ができるため、わざわざ支払いのために出かけなくてもいいことや、納付書の持ち歩きが不要なこと、さらに支払いのためにいちいち現金を持ち歩かなくて済むというのが大きなメリットです。
メリット② ポイントが貯まる

毎日のスーパーやインターネットの買い物など、さまざまな場面でポイントを貯めてお得に使う「ポイント活動」をしている方も多いでしょう。
固定資産税を現金や口座振替で支払う場合はポイントが貯まりませんが、クレジットカードやスマートフォンで決済することで、ポイントが付くというメリットがあります。
例えば、還元率1%のカードで10万円の固定資産税を払うと、1,000円分のポイントとなります。
注意点としては、カードによって還元率が違うということです。還元率の低いカードでは手数料の方が上回ってしまうこともあります。
メリット③ 家計の管理がしやすい
家計簿をつけようとしたけれど、現金で支払ったものは面倒になって書くのを忘れてしまった、という経験のある方も多いでしょう。
支出を把握するのは家計管理の基本ですが、現金ベースでは管理の手間がかかってしまいます。地方税お支払サイトを利用して固定資産税を支払うことで、カードの利用明細が残るため記録を辿るのが容易になります。
固定資産税の支払いだけでなく、普段の買い物など、日常の支払いをクレジットカードやスマートフォン決済にすることで、利用明細を家計簿代わりに使うことが可能です。
さらに家計簿管理アプリや会計ソフトと連携すれば、すべてデジタルで管理できるため、記帳の手間や記帳忘れがなく、家計管理が楽になります。
支払時期に手持ちの現金が不足してしまっている場合にも、クレジットカードやスマートフォンでの決済が便利です。固定資産税支払いの時期とカードの引き落とし日がズレるため、日程に多少の猶予が生じます。
デメリット① 領収書は発行されない
地方税お支払サイトで固定資産税をクレジットカード、スマートフォン決済で支払う場合には、領収書が発行されないというデメリットがあるので注意が必要です。
クレジットカード会社から発行された利用明細が、領収書の代わりになりますが、領収書が必要な場合は、現金で納付する方が良いでしょう。
地方税お支払サイトでは納税証明書も発行できません。公的な納税証明書が必要な場合は、別途納付先の区市町村などに申請をして発行を依頼します。申請方法などについては納付先のホームページなどで確認できます。
支払いから納税証明書に反映されるまで、時間がかかることがあります。納税証明書を急ぐ場合は、支払う前にどのくらいの期間で納税証明書が発行できるのかについても確認しておくことをおすすめします。
デメリット② クレジットの場合手数料がかかる

地方税お支払サイトを利用してクレジットカードで支払う場合、サイトの手数料(システム利用料)がかかってしまうというデメリットもあります。手数料は最低40円からで、金額に応じて段階的に上昇します。
「お得にポイントを集めるつもりがサイト手数料の方が予想外にかかってしまった」ということがないように、ポイントとサイト手数料とのバランスを計算するといいでしょう。
地方税お支払サイトの手数料はいくらになるのかは、下記で金額を入力すれば確認できます。
デメリット③ 仕様の変更がありえる
スマートフォンで決済する場合のデメリットとして、決済アプリは仕様の変更が予告なくされることがある、ということもあげられます。
特にポイント特典などは、付与基準やポイントの割合などの仕様変更がひんぱんに行われているので、決済直前にもう一度確認するなど、想定と違う結果にならないように注意することが必要です。
まとめ
不動産を所有していると支払うことになる固定資産税。固定資産税は自治体から納税通知書が届くので、それをもって支払うことになります。現在は現金だけでなく、さまざまな納付方法があるため、決済時期やポイント付与などを考えて、お得な方法を選ぶのがおすすめです。
固定資産税の支払い方をはじめ、他にも不動産には損をしないために知っておきたい情報が数多くあります。
不動産仲介会社ならではの専門的な情報を知りたい方には大手不動産6社が運営するすまいValueの活用をおすすめします。

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください


























