
土地を相続すると相続税を納税しなければなりませんが、土地が遠隔地にあって活用しづらいとか、相続人が何人もいると土地を分割するのが難しいなど面倒なことがあります。条件によっては、相続後すぐに売却したほうが良いことがあります。
この記事では、相続した土地をすぐに売却した方がよいケースや売却しなくてもよいケース、売却する場合の手順などについて解説します。

相続した土地をすぐに売却すると受けられる2つの特例
相続した土地をすぐに売却すると受けられる2つの特例があります。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例と、相続した空き家を売却した場合の特別控除です。以下、解説します。
取得費加算の特例
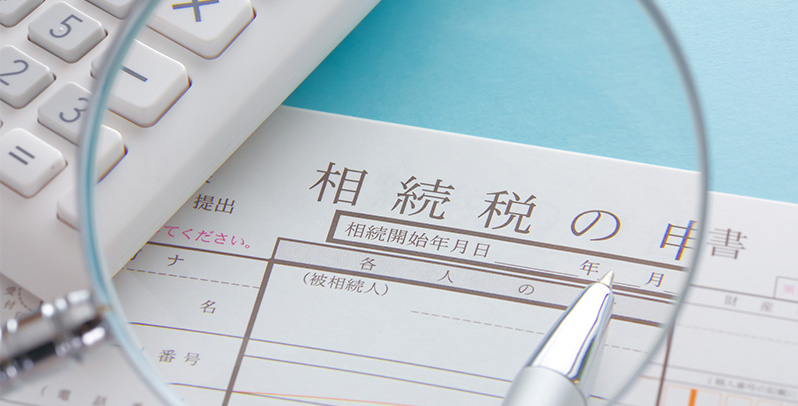
相続や遺贈で取得した土地や建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡(売却)した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例があります。
この適用を受けるための要件は、以下の3点です。
①相続や遺贈によって財産を取得していること
②相続人・受贈者に相続税が課税されていること
③その財産を相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡していること
取得費加算の特例を利用した場合の譲渡所得の計算は以下のようになります。
このうち取得費に加算する相続税額は以下のように計算されます。
つまり、納めた相続税のうち譲渡した財産にかかる部分の相続税額が取得費に加算されるということです。この適用を受けるには、確定申告に以下の書類を添付して提出する必要があります。
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 土地・建物に関する譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人から相続した居住用財産(空き家)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特別控除があります。これは空き家の発生を抑制するために設けられた特例措置で、この特別控除を受けるには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
①適用期間の要件
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 特例の適用期限である2023年12月31日までに売却すること
②相続した家屋の要件
- 相続した家屋が1981年5月31日以前に建築されたもの
- 被相続人が相続開始の直前まで家屋に居住していて、他に居住者がいなかったか、老人 ホーム等に入所していた場合は入所直前に家屋に居住していて、入所後も家屋を一定使用し、他の居住者がいなかったこと
- 家屋が事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと
③譲渡する際の要件
- 被相続人が相続または遺贈によって取得した被相続人居住用家屋か、その家屋とともにその敷地を譲渡すること
- 空き家が耐震基準を満たしていること
- 空き家を相続人が耐震リフォームするか空き家を取り壊して更地にしていること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡先が親子や夫婦など特別な関係者でないこと
- 相続のときから譲渡の時まで事業のよう、貸付けの用または居住の用に供されたことがないこと
④他の特例との適用関係
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
この特例を受けるには、確定申告書に以下の書類を添付して提出する必要があります。
- 売却した土地・建物の譲渡所得内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 売った人が相続により取得したことや家屋が1981年5月31日以前に建築されたことなどを明らかにできる資産の登記事項証明書など
- 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
- 相続開始から譲渡まで空き家であったことを証明できる売買契約書の写し、ガス閉栓証明書あるいは水道使用廃止出書など
相続した土地をすぐ売却したほうがよい場合
土地を相続した場合、慌てて売らなくても良いケースもありますが、ここではすぐに売却することを検討したほうがよい場合について解説します。
相続税の納税資金がない場合

相続税の納税が必要なケースで当座の納税資金がない場合、相続した土地を売却して現金に換えておく必要があります。相続税の納税は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。土地を売却して現金化することによって、期限までに納税しなければなりません。納税が申告期限を過ぎると、延滞税がかかる場合があるので、注意が必要です。
なお、相続税は取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に課税対象になります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算されるので、この金額以下の場合は相続税はかかりません。
土地の活用が難しい場合
土地を相続したものの自宅から離れている、貸付も難しいなどの理由で活用が難しい場合は、売却したほうがよいでしょう。
賃貸需要のある土地であれば、アパートなどの収益物件を建てて不動産収入を得ることもできますが、賃貸需要のない土地では借金だけが残ることにもなりかねません。また、土地は持っているだけでも草刈りなどのメンテナンスが必要になり、何よりも固定資産税がかかります。
活用できない土地は持っているだけでも出費が必要になるので、収益が見込めなければ売却することをおすすめします。
遺産分割がしにくい場合
相続人が複数いる場合は遺産分割することになりますが、土地の場合は単純に分割することが難しいので、相続した後に土地を売って現金化し、相続人の間で分割したほうが望ましいでしょう。相続人の間で公平性が保ちにくい場合も売却したほうがよいでしょう。
相続した土地は複数の相続人によって共有される状態になるので、その土地を売却する場合は相続人全員の同意が必要になります。売却に反対する人が1人でもいる場合は売ることができません。
固定資産税の節税がしたい場合
土地は保有しているだけで固定資産税や都市計画税の支払いが必要となります。固定資産税や都市計画税を節税したい場合、住宅を建てる計画がなければ売却をおすすめします。
住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、住宅用地が200平方メートル以下の小規模住宅用地に住宅が建っていると課税標準価格が6分の1に、都市計画区域の市街化区域では都市計画税が3分の1に減額されます。
200平方メートルを超える一般住宅用地の場合でも、固定資産税の標準価格は3分の1に、都市計画税は3分の2に減額されます。
反対に、住宅用地を更地にして保有していると、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍となるので、売却した方がよいでしょう。
相続した土地をすぐ売却しなくてもよい場合
次に、相続した土地をすぐに売却しなくてもよい場合としては、どのような場合があるか見てみましょう。ただし、いずれのケースも、相続税を支払えることが前提になります。
自宅として利用する予定がある場合
相続人が自宅として利用する予定があれば、すぐに売却する必要はありません。土地があれば自宅を建てる場合も土地購入費が要らないので、安く家を建てられます。
また、住宅用地の場合、住宅を建てると土地にかかる固定資産税の課税標準の特例が受けられるメリットもあります。将来売却する可能性があってもゆっくり考えることができます。
土地活用が見込める土地の場合

賃貸需要のある地域で収益物件を建てられるなど土地活用が見込める土地であれば、すぐに手放す必要はなく、土地活用についてじっくり考えられます。土地活用としては駐車場、戸建て賃貸、トランクルーム、一棟アパート・マンションなどが考えられます。活用ができる土地の所有者は限られており、うまく活用できれば大きな資産となります。
遺産分割が整う場合
複数の相続人がいる場合でも、遺産分割協議でその土地の相続がすんなり決まっていれば、すぐに売却する必要はないといえます。遺産分割では、分筆であっても通常単独所有になるので、その所有者がその土地を自由に活用したり、自分のタイミングで売却したりすることもできます。
相続した土地を売却する手順
次に、相続した土地をすぐ売却する場合の大まかな流れについて見ていきましょう。
遺言書の有無を確認
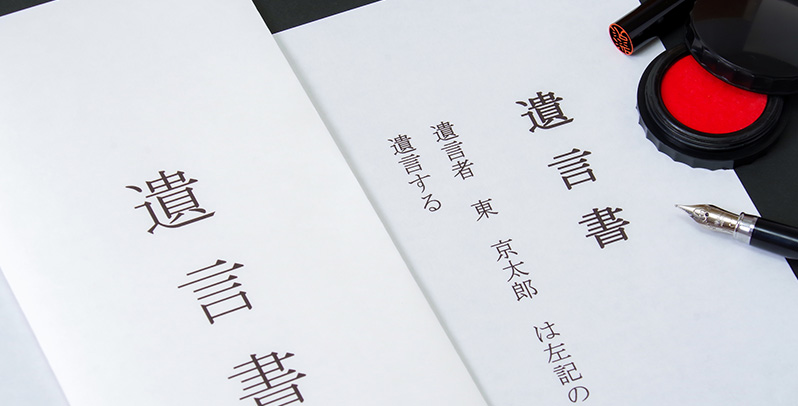
被相続人の遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、遺言書に従って相続人に遺産を分割することになります。遺言書がなければ、法定相続人による遺産分割協議を行います。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は自筆で書いただけのもので、開封する前に家庭裁判所で「検認」が必要です。勝手に開封すると遺言書の効力がなくなる場合もあります。ただし、2020年7月から始まった法務局での遺言書保管制度を利用すると、遺言書が画像データで保管され、家庭裁判所の検認手続きが要りません。原本は50年間、データは150年間保存されます。
秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密に保管するために署名捺印した遺言書を封筒に入れ、印章で封印し、それを公証人に提出します。遺言者は証人2人以上立ち会いの下で遺言書であることなどを申述し、公証人がそれを封筒に記載して署名捺印し、遺言者と証人も署名捺印します。開封には家庭裁判所で検認が必要です。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言で、公証人が遺言の内容を聞いて遺言者に代わって遺言書の原本、正本、謄本を3通作成し、原本を公証役場で20年保存します。正本と謄本は遺言者に渡され、紛失しても再交付を請求できます。
相続人と相続財産の確認
相続人と相続財産を確定します。民法では相続人の範囲と順位を定めていて、法定相続人と呼ばれ、優先順位も決まっています。
まず、必ず相続人になるのが亡くなった被相続人の配偶者です。次が、被相続人と血縁関係にある血族相続人で、相続順位は第1位が直系卑属、第2位が直系尊属、第3位が被相続人の兄弟姉妹です。相続人に当たる人が被相続人より先に亡くなっている場合は、直系卑属が代襲相続となります。
相続する財産の確認では、土地などの不動産や預貯金、保険金、貴金属などのほか、ローン残債や借金などのマイナス資産も対象になります。財産目録がない場合は、不動産については市区町村に名寄帳を申請して取り寄せれば調べることができます。
名寄帳は市区町村が固定資産税を課税するために固定資産の所有者ごとにまとめた台帳なので、被相続人の所有していた不動産が分かります。法定相続人は名寄帳の取得ができます。
遺産分割協議
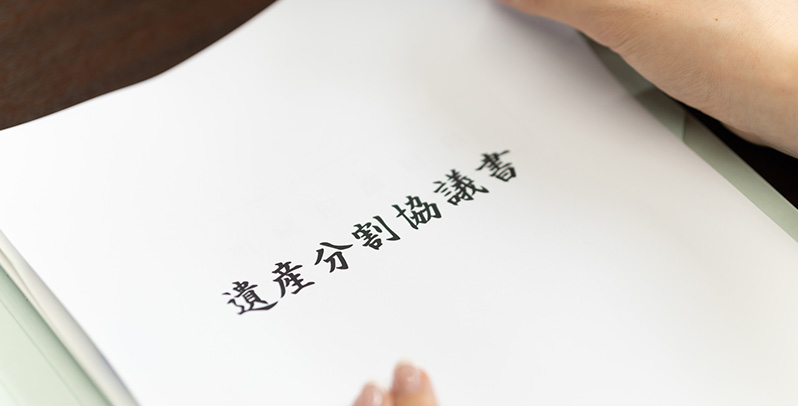
遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行って財産の分け方や相続する割合などを自由に決めることができます。遺言書があっても遺言書と異なる遺産の分割をしたいときや、遺言書に記載されていない財産を分けるときも遺産分割協議を行います。
この協議は、法定相続人が全員1ヶ所に集まって話し合う必要はなく、電話やインターネットによる通話を活用できます。しかし、決定する内容については、法定相続人全員の合意が必要になります。
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
- 現物分割:相続人が不動産や預貯金など個別の遺産をそれぞれ相続
- 代償分割:分割できない不動産や車などを一部の相続人が相続し、他の人には相続分の金銭を代償として支払う
- 換価分割:不動産や車など分割できない遺産を売却して代金を相続人で分割する
- 共有分割:遺産を共有名義にして相続する
通常、遺産分割は、これらの分割方法がいくつか組み合わされて行われます。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内なので、それまでに遺産分割協議を終えて相続税を申告、納税する必要があります。
協議が終わると遺産分割協議書を作成しますが、換価分割の場合は売却代金から経費を差し引いた金額を相続人で分割することを明記します。債務の相続などや分割の費用負担、前金が合意していることなどについても記載して、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書を法定相続人の数だけ作成し印鑑証明書とともに保管します。
相続登記
被相続人から相続人が不動産を相続すると名義変更をしなければなりません。このことを相続登記と言い、手続きは法務局で行います。この相続登記が正しく行われていない場合、第三者に対して不動産の所有権を主張できません。
相続登記には、以下の登録免許税がかかります。
- 登録免許税=土地の固定資産税評価額×0.4%
また、以下の書類が必要です。それぞれ所属の市区町村役場で入手でき、登記申請書と一緒に法務局に提出します。書類提出後1~2週間で法務局から登記識別情報通知書が届くと、名義変更が完了になります。
- 亡くなった被相続人の住民票の除票
- 亡くなった被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 相続人の印鑑証明書
相続登記については、これまではいつまでにしなければならないという期限はありませんでしたが、2021年4月の民法及び不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
法改正された理由は、現在所有者がわからない土地が多く、その面積は九州本島に匹敵するほどになっていて、これらの所有者不明の土地を解消するためです。
新制度では、以前に相続した不動産で登記されていないものも対象になります。正当な理由がなく違反した場合、10万円以下の過料が科されますので、注意が必要です。
相続税の申告・納税
相続した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税が課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で計算されますので、この金額以上の場合は相続税を申告・納税します。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生します。また、相続税の各種特例が適用できなくなるので、早めに手続きを行いましょう。
相続した土地を売却
被相続人が所有していた土地を法定相続人が分割して相続できない場合、通常行われるのが換価分割です。土地を売却してその代金を相続人の間で分割するためですが、その際に被相続人名義の土地を相続人のうち一人を代表者にして名義変更(相続登記)し、売却手続きを進める方法ですとスムーズに売却を進められます。
相続人全員の名義にして売却する方法では、相続人が多い場合、売却の手続きに全員が関わることになるので、手間がかかって煩雑になります。代表者一人に売却手続きを進めてもらい、売却代金を相続人で分割する方がスムーズに進められるメリットがあります。
売却の方法には、①親族や知人に売却する、②不動産仲介会社に仲介を依頼する、③買取専門会社に買取を依頼する、などの方法がありますが、急がなければならないなどの理由がなければ、不動産仲介会社に仲介を依頼するのが一般的です。
先述しましたが、相続財産を売却した場合に取得費の特例があり、適用を受けるには相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却している必要があります。
現金を分割
土地が売却されると、売却代金を相続人で分割します。分割方法は遺産分割協議での決定に従います。気をつけなければならないのは、代表者が土地を売却して代金を分割した場合、第三者には遺産を分けた相続なのか、代表者への贈与なのかが分からないことです。
そこで、遺産分割協議書には、相続人の一人に便宜的に名義変更し、土地を売却した後、法定相続人の間で換価分割をおこなったことを記載しておきます。この遺産分割協議書への記載を忘れると、贈与税が課される恐れがあるので注意が必要です。
土地を換価分割した場合、相続登記を申請する際にかかる登録免許税、不動産売買契約書に貼る印紙税、譲渡所得税がかかる他、売却に伴う手数料等の経費がかかります。これらの税金や経費も法定相続人の間で分割する方がよいでしょう。
確定申告
不動産の売却によって譲渡所得があった場合は、他の所得とは分離して、売却した翌年の2~3月に確定申告をする必要があります。
不動産の所有期間が被相続人と相続人を合わせて5年超の長期譲渡所得であれば、譲渡価格から譲渡費用や取得費を差し引いた譲渡所得税率は所得税率15.315%(譲渡所得税率15%と譲渡所得税額にかかる復興特別所得税率2.1%を加算)、住民税5%で合計20.315%の譲渡所得税がかかります。
5年以下の短期譲渡所得の場合は所得税率30.63%(譲渡所得税率30%と譲渡所得税額にかかる復興特別所得税率2.1%を加算)、住民税9%で合わせて39.63%です。長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに基準日は譲渡した年の1月1日です。
譲渡所得税の計算式は以下の通りです。
譲渡所得税={譲渡価格-(譲渡費用+取得費)-特別控除額}×税率
相続した不動産を売却したときにかかる譲渡費用、取得費には以下のものがあります。
- 仲介手数料
- 相続登記費
- 測量費
- 解体費
- 各種書類の発行費
相続人の代表が不動産を売却して相続人全員と換価分割した場合は、譲渡所得があれば相続人全員が確定申告をして納税します。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例や相続空き家の3,000万円特別控除の適用申請も、相続人がそれぞれ確定申告時に行います。
まとめ

相続した土地は、土地活用する予定がないときや法定相続人が複数いる場合、土地が遠方にある場合、あるいは相続財産を譲渡した場合の取得費の特例などを利用する場合など、すぐに売却したほうがよい場合が多いようです。売却して現金化することによって、換価分割もでき、確定申告をして納税するなど多様な目的にも対応できます。
土地を売却するには、信頼できる不動産仲介会社に依頼することがポイントになります。その際は、不動産一括査定サイトのご利用をおすすめします。「すまいValue」は大手不動産会社6社が運営するサイトで、最短60秒の入力で無料査定を行っていて、査定額を比較して納得できる不動産会社を選ぶことができます。
訪問査定から仲介・売却活動・引渡しまで全国の6社約900店舗がサポートしますので、安心しておまかせください。まずは「すまいValue」をお試しください。

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください

























