
不動産を相続したものの、相続税がかなりの金額になりそうで心配という人も多いのではないでしょうか。資金に不安がある場合、相続した不動産を売却して納税資金を確保するのも一つの方法です。
この記事では、相続した不動産を売却したほうがよい場合・しないほうがよい場合を具体的に紹介するとともに、不動産売却時に使える特例や特別控除についても解説します。

相続した不動産を売却したほうがよい場合
相続した不動産を手放すのには抵抗がある人もいるかもしれませんが、なかにはすぐに売却したほうがよいケースもあります。まずは、相続した不動産を売却すべき3つのケースを見ていきましょう。
相続税の納税資金が足りない場合
相続税の納税が必要にもかかわらず、当座の納税資金が確保できていないケースでは、不動産を売却して資金を確保するべきでしょう。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内の申告・納付が義務付けられており、遅延すれば延滞税や無申告加算税の追加徴収、各種特例からの除外といったペナルティを科されてしまいます。
不動産の売却には3ヶ月〜半年程度かかるのが一般的なため、判断が遅れると10ヶ月の期限を超過してしまうリスクがあります。10ヶ月の間に資金を準備できる算段がないのであれば、できるだけ速やかに売却活動を開始しましょう。
遺産分割が困難な場合
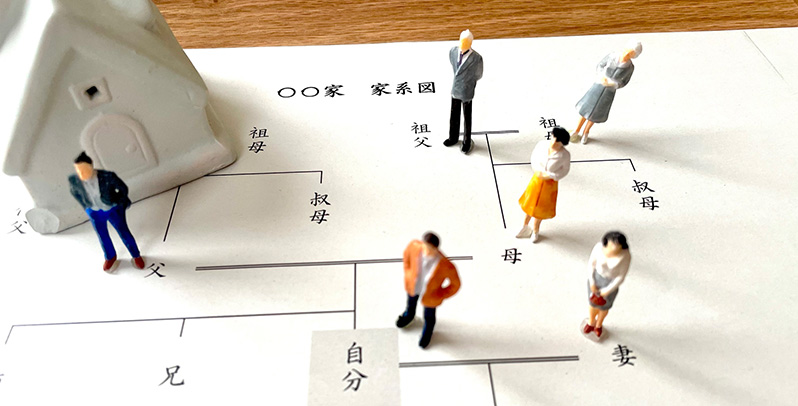
相続人が複数いて、有効な遺言書も遺されていないケースでは、遺産分割協議により相続人間で遺産分割を行うことになります。現金や預貯金のように現物分割できる財産は問題ありませんが、土地・建物などの不動産は分割することが難しく、遺産分割におけるトラブルの原因になりかねません。
不動産のままだと遺産分割の難航が予想される場合、不動産を売却・現金化したうえで遺産分割したほうがスムーズでしょう。
また、相続人で共有持分を持ち合う「共有分割」も有効ですが、共有者の一人でも反対すれば処分できなくなる点、二次相続・三次相続によって将来共有者が増える可能性がある点は要注意です。共有者が少なく、全員での合意がしやすい相続直後のタイミングで売却を検討してもよいかもしれません。
不動産売却後の遺産分割の注意点
相続した不動産を売却したうえで遺産分割を行う場合には、気をつけるべき注意点があります。
問題が生じやすいのが、相続不動産を売却するにあたって、相続人の共有名義からいったん自身の単独名義に登記を変更するケースです。何も考えずに単独登記で売却し、売却代金を相続人に振り分けた場合、この行為が「贈与」とみなされて贈与税の課税対象になってしまう可能性があります。
不動産売却後に遺産分割を行う場合には、遺産分割協議書に「換価分割である」旨を明記し、贈与ではないことを明らかにしておきましょう。換価分割とは、相続財産を現金化したうえで分割することをいいます。
不動産活用の見込みがない場合

不動産を相続したとしても、活用の見込みがないのであれば早期の売却を検討したほうがよいでしょう。活用方法が見つからないまま所有し続けていても、固定資産税が毎年かかるだけでマイナスにしかなりません。
相続した不動産の活用方法としては自宅としての実需利用のほか、アパートや駐車場などの整備による収益化が考えられます。収益物件として活用するには、立地や周辺の賃貸ニーズ、土地形状、前面道路の状況など多方面からの検討が必要です。
収益物件としてのニーズが乏しいエリアで不動産を相続した場合、居住する予定がない限りは早めに売却したほうがよいかもしれません。
相続した不動産を売却しなくてもよい場合
上で紹介した3つのパターンとは反対に、相続した不動産を急いで売却する必要がないケースもあります。どういった場合が該当するのか順番に見ていきましょう。
自宅として利用する
将来的な活用の見込みがない場合には売却したほうがよいと紹介しましたが、裏を返せば何かしら活用できるなら、売却せずに所有し続けるのも有効です。
代表的な活用方法の1つが自宅利用。相続した不動産に相続人自身が居住するのであれば、売却を急ぐ必要はありません。建物の築年数が古く、将来的に建て替えや大規模なリノベーションをする場合でも、すでに土地を所有しているので新たにマイホームを購入するよりもリーズナブルに住まいを更新できます。
また、今後売却する予定がある場合でも問題はありません。売却の決断にリミットはないので、住みながらゆっくりと考えればよいといえます。
遺産分割が整う
遺産分割がスムーズに整い、相続税の納税資金も調達できるメドも立っているなら、不動産の売却を急ぐ必要はありません。遺産分割がすんなりと整ったということは、多くの場合で不動産が単独所有(もしくは少人数による共有)になったと考えられます。
単独所有ならどのように活用してもよいですし、いつ売却しても構いません。不動産仲介会社と相談しながら、最適な活用方法を探してもよいでしょう。次に紹介するような収益物件として活用できれば、不動産を相続した強みを最大限発揮できる可能性があります。
収益物件として活用が見込める

相続した不動産が賃貸ニーズの高いエリアに位置する収益物件である場合や、今後収益物件としての活用が見込める物件である場合、相続してからすぐに売却する必要はありません。活用できれば大きな利益をもたらす可能性があるため、納税資金が厳しいなど切迫した事情がなければ、収益物件化を検討するのもおすすめです。
収益物件を新たに仕入れる場合、通常は土地購入代が費用の大きな割合を占めます。相続した土地であれば土地購入代が一切かからないため、費用の大幅な圧縮が可能。通常よりも有利な条件で賃貸経営ができる可能性があります。
不動産を売却したときの税金を節約できる特例・特別控除

相続した不動産を売却したほうがよいと判断したとき問題になるのが、売却益に課せられる税金です。相続税の納税資金への充当を目的として売却したにもかかわらず、譲渡益に対して大きな税金がかかってしまっては意味がありません。
こうした税金への対策として有効なのが、相続不動産の売却時に適用される特例や特別控除です。
具体的には、相続した土地・建物などを3年10ヶ月以内に売却した場合に節税できる「相続税の取得費加算の特例」、相続した空き家を売却した際に控除を受けられる「相続空き家の3000万円特別控除」の2つがあります。各制度の内容を詳しく解説しましょう。
相続税の取得費加算の特例
相続した不動産の売却時に使用できる1つ目の特例が「相続税の取得費加算の特例」です。この特例は相続後3年10ヶ月以内に当該相続財産を売却した場合に適用可能で、相続税額の一部を財産の取得費に加算できるというもの。取得費用が大きくなり譲渡所得が目減りするため、売却時にかかる譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が軽減されます。
相続した不動産に対しては相続税が課されるため、売却時の利益に対しても税金を課してしまうと二重課税のような状態になり、相続人の負担が増えてしまいます。こうした事態を防いで適正な税負担とするために特例が設けられているのです。
取得費に加算する相続税額の計算式
相続財産の売却時、相続税額をすべて取得費に加算できるわけではありません。次の計算式で算出される相続税額の一部を取得費に加えます。
取得費に加算できる相続税額=納付すべき相続税額 × (売却した土地の相続税評価額 / 相続税の課税価格+債務控除額)
上で計算した金額を取得費に加算したうえで譲渡所得を算定、税率をかければ売却時に納めるべき譲渡所得税額を求められます。
具体例を用いて簡単に計算してみましょう。ここでは次の条件のもとで試算します。
- 相続財産の課税価格(債務控除前):1億円
- 納付すべき相続税額:2,300万円
- 売却した土地の相続税評価額:7,000万円
- 当初の取得費:650万円(不明のため、売却価格×5%と想定)
- 売却価格:1億3,000万円
- 売却費用:600万円
取得費に加算できる相続税額=2,300万円 × (7,000万円 / 1億円)= 1,610万円
譲渡所得=1億3,000万円 −( 650万円 + 600万円 + 1,610万円)= 1億140万円
このように売却時の課税対象となる譲渡所得を減らすことにより、譲渡所得税を節税できるのです。
特例の3つの適用要件
相続税の取得費加算の特例を使うためには3つの適用要件を満たしていなければなりません。要件は次のとおりです。
- 特例適用を希望する人が相続や遺贈により財産を取得した人であること。
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- その財産を、相続開始のあった日の翌日〜相続税の申告期限の翌日以後3年が経過するまでに譲渡していること。
3点目に関しては、相続税の申告期限が「相続を知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められているため、実質的に「相続開始日から3年10ヶ月以内に売却していること」と読み替えることができます。
相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除

相続した不動産を売却する際に利用できる特例の2つ目は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この特例により、被相続人が住んでいた自宅や自宅用敷地を相続・遺贈により取得した人が当該物件を一定期間内に売却した場合、要件を満たせば、売却時の譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
例えば、相続した不動産を5,000万円で売却、取得費を売却価格の5%(250万円)、売却活動にあたって500万円の費用がかかったとしましょう。特別控除を活用すると、売却時の譲渡所得は次のとおり計算できます。
譲渡所得=5,000万円 −(250万円+500万円)− 3,000万円 = 1,250万円
こちらの特例も譲渡所得を低減できるため、売却時にかかる譲渡所得税の節税効果を期待できます。
特別控除の4つの適用要件
上記の3000万円特別控除の適用を受けるには、次に挙げる4つの要件を満たしている必要があります。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で暮らしていた住宅であること。
- 1981年5月31日以前に建築された戸建て住宅であること。(旧耐震基準で建てられた住宅)
- 相続から売却まで空き家であり、居住用や事業用・貸付用として利用されていなかったこと。
- 建物が一定の耐震基準を満たすか、建物を取り壊して更地にすること。
1点目に関して、要介護認定を受けて老人ホームに入所せざるを得なかったケースなどでは、一人暮らしの被相続人が入所直前まで住んでいた実績があれば要件を満たすものとされます。
また、2024年1月以降の譲渡から4点目の要件が一部変更され、譲渡時に要件を満たしていなくても、譲渡年の翌年2月15日までに耐震化や解体が完了すれば適用対象となります。相続人が3人以上いると控除額が最大2,000万円に減額される点も注意が必要です。
取得費加算の特例と相続空き家の3,000万円特別控除は併用不可
相続不動産の売却時に適用可能な「取得費加算の特例」と「相続空き家の3000万円特別控除」は併用が認められていません。どちらか一方を選択しての適用となります。ただし、相続した不動産が店舗併用住宅の場合、店舗部分に取得費加算の特例を適用し、住宅部分は相続空き家の特別控除を適用するといった使い方は可能です。
相続空き家の特別控除は取得費加算の特例に比べて要件が厳しく、相続空き家に該当しない場合は取得費加算の特例の適用を前提に考えるしかないでしょう。両者とも利用できるケースではどちらか有利なほうを選択したいところです。
一般的には、相続空き家の特別控除における最大3,000万円という控除額は大きいので、相続税額が相当に高いケースを除き、3,000万円特別控除のほうが有利かもしれません。
被相続人と同居していた場合は
不動産の相続を受ける人のなかには、親など被相続人と同居していた自宅を相続するケースもあるでしょう。被相続人と同居していた家を売却する場合、マイホーム(居住用財産)としての特例や特別控除を受けられる可能性があります。
主な特例・特別控除としては「マイホームの3,000万円特別控除」と「所有期間10年超の軽減税率の特例」が挙げられます。
「マイホームの3,000万円特別控除」は自分が住んでいる住宅やその敷地の売却時、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられるという特例です。被相続人と同居していた人が相続を受けた場合、要件上の「居住用財産」に該当するので適用可能となることがあります。
マイホームの所有期間が10年を超えるとき、長期譲渡所得として軽減税率が適用されるのが「所有期間10年超の軽減税率の特例」です。マイホームを相続した場合、通常相続人が被相続人の所有期間を引き継ぐとされるため、被相続人の取得時点から10年超であれば特例が受けられます。
また、この特例は3,000万円特別控除との併用も可能であり、大きな節税効果が期待できるでしょう。
まとめ
不動産を相続したときには相続税の納付が必要になる場合があります。相続した不動産の評価額が高いと相続税も大きな金額となるため、納付資金の用意が難しければ、不動産売却で必要資金をまかなうのも選択肢の一つです。
相続した大切な不動産を売却する際は、経験豊富で信頼できる不動産仲介会社に依頼することが何よりも重要です。相続税対策や相続問題の解決を目的に不動産売却を検討しているなら、大手不動産会社6社が運営する不動産一括査定サイト「すまいValue」を活用してはいかがでしょうか。

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください

























