
マンション、戸建て住宅など「家」を売りたいと考えるなら、事前に売却の流れをつかみ、ポイントを押さえることが重要です。この記事では、家を売る際にかかる費用、必要書類、注意しておきたいポイントについて解説し、合わせて築古、再建築不可など売りにくい物件の売却方法についてもお伝えします。

家を売却する流れ
家を売却するとき、どういう手順で進んでいくのでしょうか。売主様の立場から見た家の売却のおおまかな流れを解説します。
相場の確認
マンション・戸建て住宅など売りたい不動産がおよそいくらで売れるのかを知るために、相場を確認します。
査定の前に、相場観をつかんでおけば、査定結果が高いのか低いのかを判断する目安になります。
下記のサイトを利用すれば、プロでなくともある程度は調べることが可能です。
また、不動産一括査定サイトも相場を確認するのに役立ちます。
査定の依頼
売却したい家の相場をつかんだら、次に物件の査定を依頼します。査定は偏りを避けるため必ず複数の不動産仲介会社に依頼しましょう。
査定は、不動産仲介会社に個別に依頼する方法もありますが、一度の入力で複数の不動産仲介会社に依頼できる不動産一括査定サイトを利用するのが便利です。
査定には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
机上査定は、実際に物件を見ることなく、物件概要や取引データをもとに査定する方法です。
訪問査定は、物件概要や取引データをふまえたうえで、実際に現地の状況を確認して査定する方法のため、具体的に売却を検討している方におすすめです。
机上査定は、売却を検討している段階の方に向いている方法ですが、この段階でできるだけ多くの不動産仲介会社とコンタクトを取り、訪問査定を依頼する不動産仲介会社を選ぶという利用の仕方も可能です。
不動産を売却する際には、必ず訪問査定を依頼します。立ち会いが必要なため手間と時間はかかってしまいますが、査定の精度は高くなります。
また、訪問査定は不動産仲介会社の対応を判断する機会としても活用できます。売却の希望「早く売りたい」「適切な価格で売りたい」なども伝えると、事情にあった売却プランを提案してくれます。
不動産仲介会社と媒介契約
査定結果を見て、不動産仲介会社を選んで正式に売却の仲介契約を結びます。この契約を「媒介契約」といいます。
売主様が不動産仲介会社と結ぶ媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
媒介契約にかかる注意点は後述します。
売却活動の開始
不動産仲介会社と売主様の間で媒介契約を結んだ後、不動産仲介会社は、売主様の家の売却活動を開始します。
不動産の購入希望者を募る方法は、不動産ポータルサイトへの広告出稿、レインズ(指定流通機構)への登録、店頭での案内などです。
売主様は物件に対する買主様からの問い合わせに回答したり、内覧会を開催したりするなど、必要に応じて対応します。これらは、不動産仲介会社もサポートをしてくれるので安心です。
専任媒介契約、専属専任媒介契約であれば販売活動がどの程度進捗しているか、不動産仲介会社から定期的に状況報告があります。一般媒介契約の場合は報告義務はありませんが、報告をする会社もあります。
買主様と売買契約
買主様が見つかったら、買主様との交渉を経て正式な売買契約を締結します。
買主様に対して不動産仲介会社が重要事項説明を行い、売主様と買主様で売買契約を締結、売主様は手付金を受領します。
売主様も重要事項説明書をはじめ、売買金額や引渡し時期などの契約内容に不備・不明点がないかよく確認します。契約に先立って必要書類と諸費用の確認は忘れずに行いましょう。
売主様の用意する書類としては、本人確認書類、実印、印鑑証明書、銀行口座の通帳(コピー)、ローン残高証明書などがあります。また、仲介手数料、印紙税などの諸費用が発生します。
滞りなく売買契約を結ぶために、事前に不動産仲介会社に相談をして、契約当日に向けて準備を進めておきましょう。
決済と物件の引渡し
売主様・買主様間の売買契約が済んだら、物件の引渡し準備をします。
通常、決済と引渡しは同日に行います。当日は、残代金を受領して領収書の発行をします。住宅ローンの残債がある場合は、売却代金で一括返済を行い、抵当権抹消登記を行います。
また、固定資産税の日割り清算、必要書類と鍵の引渡しなどを行います。
確定申告
家を売却した翌年の2月16日~3月15日の期間内に確定申告をします。
売却によって売却益(譲渡所得)が出た場合は後述の譲渡所得税がかかりますし、税制で定められた特例を利用する場合も確定申告は必要です。
売却によって損失が出てしまった場合は、確定申告の義務はありません。ただし、譲渡損失は他の所得と損益通算ができ、節税になることがありますので、必ず確認するようにしましょう。
税務処理については税理士にご依頼されるか、ご自身で行うこととなります。すまいValueの各運営会社では税理士による無料相談会も定期開催しています。
家を売却するための費用

家を売るためには仲介手数料などの諸費用がかかり、売った後は売却益に対して譲渡所得税の納税が必要になります。ここでは、家の売却にともなう費用や税金について説明します。支払いの段階になって足りないということがないように、あらかじめ必要となる金額と支払時期を確認しておきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は家の売却が決定し成約した際に、不動産仲介会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法では上限額が決められていて、200万円以下の部分は5%、200万円超~400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%となっています。したがって、例えば、1,000万円の成約の場合、計算式は以下のようになります。
200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%+消費税=39万6,000円
通常は、このような計算が面倒なので、以下の簡単に計算する速算法が使われます。
200万円以下の場合 成約価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下の場合 成約価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超の場合 成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税
例えば、1,000万円の成約の場合、以下のようになります。
1,000万円×3%+6万円+消費税=39万6,000円
仲介手数料を支払う時期は、一般的には売買契約成立時に半金、引渡し時に半金を支払うことが多いのですが、不動産会社によって異なるので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
印紙税
印紙税は、印紙税法に定められた売買契約書のような課税文書に対して課税されます。不動産売買契約書に収入印紙を貼って消印をして納税しますが、通常、2通作成するので、売主と買主がそれぞれ負担します。売買契約のときに必要になります。
契約金額によって税率は下表のように変化しますが、記載金額が10万円を超えるものについて、2014年4月1日から2024年3月31日までの間に作成された契約書には軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
登録免許税(抵当権抹消登記、相続登記など)
住宅ローンの支払いが残っている場合、金融機関は万一返済されない場合に備えて、家や土地に抵当権を設定しているので、家を売却する前にローンの残債を一括返済して登記簿謄本から抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消は、司法書士が代理となり法務局で行ってくれますが、このときに法務局に抵当権 抹消の登録免許税を納めます。この登録免許税は不動産1物件につき1,000円なので、戸建て住宅の場合、土地1筆に建物1棟が建っていれば、登録免許税は2,000円となります。
繰上返済手数料
繰上返済手数料は、住宅ローンの残債を一括返済する際に金融機関に支払う手数料です。金融機関によって手数料が変わり、手続き方法によっても変わります。一括繰り上げ返済を行う場合は、金融機関に事前に問い合わせしてみるといいでしょう。
司法書士への報酬
家の売却では、司法書士に抵当権抹消を依頼するので、司法書士への報酬が発生します。報酬は司法書士によって異なりますが、10,000~30,000円程度です。
譲渡所得税
家と土地を売却した場合、購入価格より高く売れた場合には、譲渡所得税がかかります。不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超えるものは長期譲渡所得となり、以下の所得税と住民税がかかります。このうち、復興特別所得税は東日本大震災の復興に必要な財源として規定され、2013年から2037年まで課されます。
譲渡所得税の計算式は、以下のとおりです。
課税譲渡所得=収入金額(売却額)-取得費用-譲渡費用
短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税額2.1%
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税額2.1%
しかし、居住用財産の売却では、譲渡所得がプラスになっても3,000万円特別控除という特例があるので、3,000万円を超えるようなケースはあまりありません。
また、譲渡所得がマイナスの場合にも特例があり、買い替えをするかしないかで特例が変わります。
引越し費用
家の売却にともない引越しをしますので、それにかかる費用が必要になります。買い替えをする場合は、住んでいた家から新居への引越しになりますが、もし一時的に仮住まいが必要ならば、引越しを2回することになるうえ、仮住まいの家賃も必要になります。
引越し費用で気をつけなければいけないのは、3~4月の引越しシーズンにぶつかると、希望の日に引越しできなくなったり、引越し代が高くついたりするので、早めの手配をおすすめします。
測量費用
戸建て住宅を売却する場合、土地の面積や隣地との境界があいまいなときは測量や境界確定が必要となります。測量は土地家屋調査士に依頼して行い、測量費用は一般的には売主の負担になります。
土地は登記されたものでも、測量をした年数が古いと境界が正確でない場合があり、登記簿上の面積と実際の面積が異なると売買代金に影響するので、正確な面積を把握する必要があります。特に、市街地の場合は、土地の単価が高いため、隣地との境界争いを防ぐために測量が行われるケースが多くなります。
測量には、現況測量と確定測量があります。現況測量は所有者の依頼だけで作成されるのに対して、確定測量は土地家屋調査士と隣地の所有者が立ち会って行われます。現況測量は1日で作業を終了することも多く、費用も確定測量ほどかかりません。
登記を目的にした測量は土地家屋調査士に依頼が必要です。確定測量は図面作成まで含めて1~3ヶ月必要で、費用の相場は100~130㎡の住宅地の場合、隣も民間の住宅地であれば35~45万円程度、隣地が公有地の場合は行政の確認が必要になるので60~80万円程度になります。
解体費用
家の築年数が経っているため、古家を解体し更地にして売却するときは、解体費用がかかります。解体費用の相場は、木造住宅の場合、坪当たり5万円ほどになります。例えば延床面積が30坪なら90~150万円が相場です。
解体費用は、工事会社や立地環境によって変わります。立地が、住宅密集地で重機が入っていけないような場所であるとか、重機の使用が制限されるような場所では、工期が延びたりして解体費用が高くなることもあります。
不動産仲介会社に査定・売却依頼を行う際の必要書類
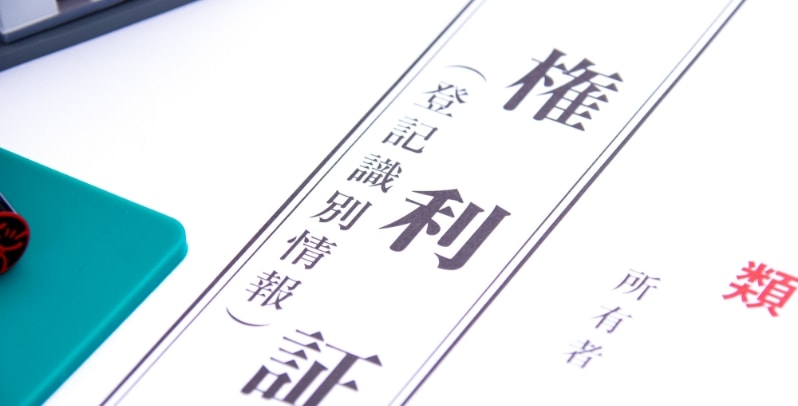
家を売却するには、不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ必要がありますが、その段階で準備しなければならない書類は、下記のように登記事項証明書・登記簿謄本や売買契約書など多くの書類が必要になります。以下で順次説明します。
登記事項証明書、登記簿謄本
登記事項証明書は不動産の所有者の住所、氏名、所在、大きさ、構造、地目などが記載された証明書です。オンライン化されている登記所から発行されます。オンライン化される以前は紙の登記簿が原本だったので、登記簿の写しとなる登記簿謄本が中心でした。証明内容はどちらも同じで、法務局で申請して取得します。
登記識別情報、登記済権利証
登記識別情報は、不動産の権利者であることを公的に証明するため、法務局から名義人に対して発行される12桁のアラビア数字その他の符号の組合せからなるパスワードです。2005年3月に不動産登記法が改正され、インターネットでの申請が可能になりました。不動産登記がオンライン化される以前は、登記済権利証が発行されていました。この登記識別情報または登記済権利証を買主に渡して移転登記が行われると、不動産の所有権は買主樣に移ります。
売買契約書
売買契約書は物件の購入時に以前の売主との間で交わしたものです。契約日や引渡し日、売買代金や手付金の金額、物件の状況、付帯する特約などが記載されていて、物件を売却する際に、買主と新たな売買契約書を作りますが、譲渡所得税を計算するのに必要となります。
重要事項説明書
重要事項説明書は、宅地建物取引業者が売買契約上重要な事項を説明した書面です。物件の内容や対象不動産の権利関係、法令上の制限、不動産の状態やその見込み、売買契約の条件に関する事項などが記載されています。例えば、私道の負担や周辺の下水処理場などの嫌悪施設の有無、ガスや電気の供給状況などが記載されています。
土地の測量図、境界確認書
土地の測量図や境界確認書は、一戸建てや土地の売買に必要な書類です。戸建て住宅や土地の売却時は測量の義務はありませんが、面積や境界が不明瞭だと隣接地の所有者とトラブルが起きることが予想されます。
測量図には、確定測量図、現況測量図、地積測量図の3種類があり、境界確認書は測量の結果確定した境界を証明する書類となります。境界線が未確認の場合、隣接地の所有者に了解をとって測量図を作成するようにしましょう。
固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書
固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書は、固定資産税の納税額の確認、所有権移転登記の際の登録免許税の算出に必要な書類です。
固定資産税は1月1日時点における所有者に課税されますが、引渡しを行った日以降の固定資産税を買主樣が負担するのが一般的です。
物件の図面、設備の仕様書
物件の図面や設備の仕様書では、間取りや設備状況が確認できます。不動産仲介会社がお互いに物件情報を共有できるレインズ(指定流通機構)などに間取図などの物件情報を掲載することによって、内覧数のアップを図ることができます。売却をスムーズに行うために、物件の図面や設備の仕様書はあらかじめ準備しておくといいでしょう。
建築確認済証、検査済証
建築確認済証及び検査済証は戸建て住宅の売却の際に必要となります。物件が建築基準法で定められた基準で建築されたものであるかを証明するもので、採光やシックハウス対策などに適合している証明になり、買主樣も安心できます。
マンションの管理規約、使用細則、維持費関連書類
マンションの管理規約や使用細則、維持費関連書類は、マンションを売却する際に必要となる書類です。ペットの飼育など、そのマンションの生活上の注意点や管理費、修繕積立金などが記載されているので、月々の支払いにも関連し、購入者にとって必須の書類です。
耐震診断報告書
1981年6月の新耐震基準が導入される前の物件を売却するときに、耐震診断を受けている場合は報告書を提示します。
アスベスト使用調査報告書
アスベストに関する調査を受けている場合は、アスベスト使用調査報告書を提示します。
引渡しの際の必要書類

買主樣と売買契約を結び、物件を引渡す際に必要となる書類には、本人確認書類や実印・印鑑証明書などがあります。以下に説明します。
本人確認書類
本人確認書類とは、売主が間違いなく本人であることを証明する書類です。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付の書類が必要です。
実印、印鑑証明書
印鑑証明書の有効期限は3ヶ月なので、発行から3ヶ月以内のものを用意します。物件が共有名義となっている場合は全員の実印、印鑑証明書を揃える必要があります。
銀行口座の通帳
売却代金を買主樣に振り込んでもらうために、銀行口座の通帳が必要になります。銀行名(コード)、支店名(支店番号)、口座名義、口座番号などが分かる通帳または通帳のコピーを用意し、振り込んでもらう際に口座情報を買主樣に伝えておきます。
ローン残高証明書、ローン返済予定表
ローン残高証明書あるいはローン返済予定表は、住宅ローンを返済中で、住宅ローンの残債がある場合、残債の総額を証明するために必要な書類です。
住民票
不動産の登記上の住所と売主の現住所が違う場合に準備します。共有名義の場合は全員の住民票が必要です。住民票の有効期限は発行から3ヶ月以内です。
パンフレット、広告資料
購入時の物件のパンフレットや広告資料などがあれば、有効な物件情報になるので買主様に渡します。
家を売却するときの注意すべきポイント
家を売却する際には信頼できる不動産仲介会社とよく相談して進めることが大切です。さらに失敗しないために押さえておきたいポイントがいくつかあります。
住宅ローンが完済できるか確認する
住宅ローンを完済した後での売却や、相続で受け継いだ家の売却の場合は、特に問題にはなりませんが、持ち家の売却活動をはじめる前に、まず確認しておかなければならないのが住宅ローンの残債の額です。
住宅ローンが残った状態だと、抵当権の抹消ができないためです。抵当権とは住宅ローンに対する担保として金融機関が設定するものであり、住宅ローンを組んで購入する不動産に対して設定されます。
売却時には抵当権を抹消した状態で引渡さなければならないため、住宅ローンが残っていると売却が事実上不可能になるのです。そのため住宅ローンの残債がある場合、売却代金で一括返済することになります。
売出価格を決めるときには、その価格で住宅ローンの完済が可能かどうかを必ず確認します。成約価格が想定よりも低く、住宅ローン残債を売却代金だけでまかなえない場合は追加資金が必要になるため、準備をしておく必要があります。
成約価格は売出価格よりも安くなることも想定した上で、計画を立てることが大切です。
査定は複数の不動産仲介会社に依頼する
家の査定は不動産仲介会社に依頼しますが、会社によって査定額が異なることがあります。査定の基準や積算方法は各社大枠では同一になっているものの、法的に決まっているわけではないため細かいところでは各社それぞれの経験や積算方法で査定をしているためです。
不動産仲介会社によっては戸建て住宅が得意な会社、マンションが得意な会社、オフィス物件が得意な会社など得意な分野や得意なエリアがあるという理由もあります。
複数の不動産仲介会社に査定を依頼したほうがいいのは、一社だけの査定結果だけを見ていたのではどうしても査定価格に偏りが発生してしまうためです。一社だけでは気づけなかった物件の強みや弱みを、別の不動産仲介会社が見つけてくれるかもしれません。
売却する家のアピールポイントとウィークポイントを知るためにも、複数の不動産仲介会社に査定を依頼することをおすすめします。
査定は、売主様が不動産仲介会社を見極める機会でもあります。担当者の対応や説明の内容などを比較検討して、どの不動産仲介会社がより信用できるのか、不動産仲介会社を見極めるつもりで複数の会社に依頼することもできます。
複数の不動産仲介会社に個別にアポイントを取るのは手間がかかります。一度の入力で複数の不動産仲介会社に査定を依頼できる不動産一括査定サイトを賢く利用しましょう。
販売戦略に沿って仲介契約を選ぶ
先述したとおり、売主様が不動産仲介会社と結ぶ媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれ特徴や違いは次の表のとおりです。
| 複数会社への依頼 | レインズへ※の物件登録義務 | 契約期間 | 業務の報告義務 | 自ら探した買主様との直接契約 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | できない | 媒介契約締結後5日以内に登録 | 3ヶ月 以内 | 1週間に1回以上 | できない |
| 専任媒介 | できない | 媒介契約締結後7日以内に登録 | 3ヶ月以内 | 2週間に1回以上 | できる |
| 一般媒介 | できる | なし | 定めなし(通常3ヶ月以内) | なし | できる |
※レインズ:Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。レインズには全国の不動産情報が登録され、レインズ会員である不動産仲介会社は自由に物件情報を閲覧できます。
媒介契約はその種類によってメリット・デメリットがあります。
一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社に同時に仲介を依頼できる契約です。売主様がご自身で見つけてきた相手方との契約も有効です。複数の不動産会社が売却窓口の担当になってくれることがメリットといえますが、その一方で、窓口の複数社と販売の状況をやり取りしなければならないなど、手間も多くかかります。
一般媒介契約には明示型と非明示型があります。明示型は他の会社に依頼しているかどうか通知する必要があり、非明示型は他社に依頼していることを通知する必要がない契約です。
専任媒介契約、専属専任媒介契約は他社への依頼ができないというデメリットもありますが、そのぶん、依頼した不動産仲介会社の充実した売却活動や手厚いサポートが期待できます。
すぐに売れることが予想できる人気のあるマンションは一般媒介契約にし、少し売れにくいと思われる物件では専任か専属専任にするなど、物件に合わせて媒介契約を結ぶといいでしょう。
アピールポイントを整理しておく
売却を成功させるには、売却する物件のプラス面とマイナス面を把握しておくことが大切です。特に、購入希望者が魅力を感じるような長所はどこかを見つけておきましょう。
内覧の時など、売主様自身が見学者に物件について説明するシーンも予想されます。少しでも良い印象を与えるためにも物件のアピールポイントをまとめておき、物件の良いところを伝えるようにすれば、成約の可能性も高くなります。
「2階の窓を開けるととても気持ちのいい風が入ります」「家の柱はすべて国産杉です」など、どんな細やかなことであっても一つでも多くアピールポイントをまとめておくことをおすすめします。
また逆に、物件の欠陥もきちんと把握しておきましょう。もし欠陥があるにもかかわらず、買主様に伝えずに売買契約を締結してしまうと「契約不適合責任」に問われることもあります。契約不適合責任であった場合、契約解除や損害賠償請求だけでなく代金減額請求や追完請求をされる可能性があります。
内覧会を効果的に行う
買主様にその家の魅力を伝え、具体的に購入をイメージしてもらうためには、内覧会の開催も有効です。
内覧会を開催する際には、準備が大切です。掃除や片付けは念入りに行いましょう。特に気になるのが、バス、トイレ、キッチンなどの水回りです。プロにハウスクリーニングを依頼することも検討してみてもいいでしょう。
売却価格をアップするため、インテリアや家具の配置も大切なポイントです。おしゃれな家具をレンタルし、インテリアコーディネーターに依頼して配置してもらう「ホームステージング」という方法もあります。
内覧会を開催する場合は、経験のある不動産仲介会社のサポートを受けましょう。
売りにくい家を売却する場合
築年数が浅い、駅が近い、間口が広いなど、人気が出やすい、売れやすい物件がある反面、さまざまな理由で売れにくい家もあります。そんな家を売却したい場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。
ここでは築古の戸建て住宅、再建築不可物件、既存不適格建築物の3パターンで考えてみます。
築古の戸建て住宅
家は築年数が浅いほど高値で売却しやすいものですが、人によって「新しい」「古い」の感覚は違います。どのくらいが築古となるのでしょうか。
家を売却する際の判断基準としては、築年数が20年以上であることと、旧耐震基準の建築であることの2つがあります。
【築年数が20年以上】
建築から20年経過した家は、物件価値が半分以下になり、30年以上経過した家は、建物としての価値はほとんどないと判断されてしまうことが多いようです。
これは住宅の法定耐用年数(不動産の減価償却費用を算出するために国が決めた年数)が下記のように定められていることが考え方のもとになっています。
法定耐用年数は以下のように定められています。
| 建築材料・構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
| 鉄筋コンクリートブロック造(CB造) | 38年 |
| 鉄骨造 | 34年 |
| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 47年 |
| PC造(プレキャスト・コンクリート造) | 47年 |
【旧耐震基準の建築】
1981年5月31日までに建築確認を受けた旧耐震基準の物件は、耐震性が今の基準に比べて低いため、耐震工事をしても、現在の基準には追いつかない可能性が高いため、価格が下がる傾向にあります。
そのまま通常通り売却する
まず考えられるのが、そのまま通常通り不動産仲介会社に依頼して売却する方法です。
交通の便が良い場所であれば築古物件でもニーズはありますし、なかには築古の家を購入して、自分好みの家にフルリノベーションしたいという人もいます。
土地と建物の両方を所有している場合、中古住宅としてではなく、古い家付きの土地として売却する方法があります。古い家には価値がほとんどないため、土地単体の価格とほぼ同等で取引されることが多いからです。
こうすると中古住宅を求めている人々だけでなく、土地を購入したい人々の両方にアピールすることができるため、売却できるチャンスが広がります。
土地を求めている買主様にとっても、解体費用を含めても、比較的安価に土地を手に入れることができるというのは魅力です。
また、家付きで売却する場合、居住用住宅の軽減税率が適用され、固定資産税が高くなることを避けることができます。土地を更地にした場合、固定資産税が上がってしまいますが、家付きならその心配はありません。
売却期間が長引くと家の管理コストはかかりますが、解体費用と手間がかからないのは大きなメリットといえるでしょう。
フルリノベーションして売却する
築古の家でも、建物部分をフルリノベーションして、まるで新築のような見栄えに仕上げたり、設備を新しく入れ替えたりすることで、購入希望者が現れやすくなります。
ただし、リノベーションやリフォームには相応の費用がかかります。費用を売却価格に上乗せすると、売却価格が高くなって売れにくくなくなることもあります。
解体して更地として売却する
築古の家の場合、評価額がつくのが土地のみで建物部分の評価額が0円となることがあります。こういった場合は、解体して更地にし、土地として売却する方法もあります。
解体には費用がかかるため、売出価格の設定にこれを反映させると、売出価格が少し高くなります。また解体によって1月1日時点で更地になっている場合、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、注意が必要です。
不動産会社による買取
築年数が古くて個人の買主様が見つからなさそうなとき、あるいは売却を急いでいるときには、不動産会社の買取も検討していいかもしれません。
不動産会社による買取は売却までのスピードが速く、多少の難のある物件でも売却できるのがメリットですが、売却価格が通常より2~3割ほど安くなってしまうというデメリットがあります。
再建築不可物件
敷地が公道に面していない、または面していても道路の幅員や間口が基準(間口2メートル、道路幅員4メートルなど)に達していない場合、建築基準法の接道義務に違反しています。この違反がある場合、原則的に新たに 建築許可を得ることが不可能になります。
こういった敷地にすでに建築されている再建築不可物件は、リフォームすることは可能ですが、建築確認が必要な工事については行政からの建築許可が得られないため、新築や増築などができません。
再建築不可物件は既存の建物を小規模リフォームして利用する以外に活用の選択肢がなく、担保価値が低いため、買主様がローンを組みにくいというデメリットもあります。老朽化や天災などによって既存建物が倒壊したとしても再建築は不可ですから、将来的に活用できない土地を所有するというリスクもはらんでいます。
そのため、再建築不可物件は買主様が現れにくい物件となっています。
隣地所有者に売却する
再建築不可物件の売却を考えたら、まずは隣地所有者に相談をすることをおすすめします。隣地所有者が増築を考えている場合は買取ってくれる可能性があります。
また、買い取りできない場合も、隣地を売却や賃貸してもらうことはできるかもしれません。次項で解説するように、それによって土地の間口を広げ、再建築可能物件とすることができる可能性もあります。
再建築可能にして売却する
再建築不可物件の売却を考える際には、再建築が可能にできないかを探ってみることが大切です。
【セットバックを検討する】
もし土地が接道する道路が、建築基準法の「2項道路」(幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道)である場合、セットバック(道路中心線からの水平距離2mを道路の境界線とみなすこと)を実施すれば、再建築が可能になる可能性があります。
【隣地の土地を購入する】
接道義務では、道路に接する間口(最低2m以上)も重要です。間口が2m未満の場合、再建築不可になりますが、隣地から土地を購入したり、借りたりすることで間口を広げ、再建築可能な物件とすることができます。このため、隣地の所有者との協議が必要になります。
【但し書き道路の申請】
建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と規定されていますが、周囲に十分な空地があるなど安全性が確保できる場合には、例外が認められることがあります(この例外を「43条但し書き道路」といいます)。市町村の建築指導課や都市計画課などに申し出て許可を得れば建築が可能になることがあります。
上記をクリアし再建築が可能な物件にすることができれば、通常の物件として売却することが可能です。
不動産会社による買取
再建築不可物件のため個人の買主様が見つからなさそうなとき、あるいは売却を急いでいるときには、不動産会社の買取も検討していいかもしれません。
既存不適格建築物
既存不適格建築物とは、その家を建築した当時は適法だったものが、法令の改正により基準に合わなくなった建築物をいいます。建築基準法3条2項には既存不適格建築物は現行法の規定適用から除外されるという規定があります。
既存不適格建築物を所有し続けることは、特に問題はなく、罰則の対象になることはありません。ただし、建て替えをしたり建築確認が必要な大規模な増改築などをしたりする場合は、現行の法律に従って行わなければなりません。
事実を告げた上で通常通り売却する
既存不適格建築物は違法建築物ではありません。そのため、事実をきちんと伝えた上でなら、不動産仲介会社の仲介によって通常の物件と同じように売却することは可能です。売却に際しては重要事項説明書などで既存不適格建築物であることを必ず伝えなければなりません。
しかし、買主様にとっては住宅ローンが組みづらい、建て替えやリフォームが制限されるなどの不利益があるため、値引きを要求されてしまうことがあります。売却額が多少安くなっても、手間をかけずに早く売却したいという場合の選択肢として検討してもいいでしょう。
既存不適格内容の是正後に売却する
既存不適格建築になってしまう家を売却するために、不適格部分の是正を行うことで、既存不適格建築ではなく、通常の中古物件として売却することも考えられます。
建ぺい率や容積率オーバーの場合、隣地の所有者に売却予定の有無を尋ねたり、指定の建蔽率、容積率にあわせるために減築する場合かかる費用を工務店などで確認したりするなどして是正が可能かどうか検討してみましょう。
是正により、買主様がローン審査に通りやすくなるため、購入しやすくなるというメリットがあります。
解体して更地として売却する
既存不適格建築の住宅がある宅地の場合、評価額がつくのが土地のみで建物部分の評価額が0円となることがあります。
こういった場合は、解体して更地にし、土地として売却する方法もあります。
不動産会社による買取
既存不適格建築物の場合も、不動産会社の買取がありえます。
まとめ

家の売却を成功させるには、この記事で紹介したようなポイントを押さえておくことが大切です。なかでも重要なのは信頼できる不動産仲介会社を選ぶことです。売却のパートナーにどんな相手を選ぶかに売却の成否がかかっているといっても過言ではありません。
不動産一括査定サイトのすまいValueは、実績豊富な大手不動産6社の運営で、売却活動も頼りになります。ぜひご活用することをおすすめします。

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください

























