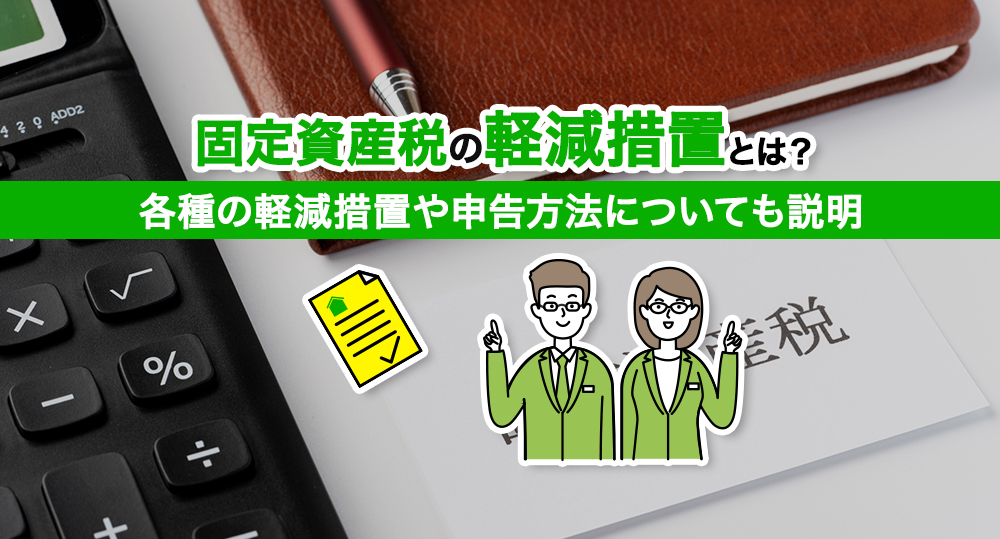
マイホームを購入すると賃貸住宅時代にはなかった固定資産税の支払いがあり、一定の負担を感じる方もおられると思います。固定資産税には軽減措置があることをご存じでしょうか。
この記事では、固定資産税とはどのような税金なのか、支払い先、税率などについて説明するとともに、固定資産税における各種の軽減措置や申告方法について解説します。

固定資産税とはどのような税金か
まず、固定資産とはどのような資産かについて説明します。固定資産とは土地や建物、機械など現金化しにくい資産を意味します。これに対をなすのが流動資産で、現金化しやすい資産を意味し、現金や預金、取引で生じる手形、売掛金などがそれに該当します。
固定資産には住宅地や田畑、山林などの土地、また住宅や工場などの家屋、さらに事業者が所有する飛行機や船、車両、機械設備などの減価償却資産の3種類があります。このような固定資産に市町村は市町村税(東京都の場合は都税)を課税していて、これを固定資産税と言います。
固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在、個人や法人が所有する土地、家屋、減価償却資産などの固定資産に対して市町村(東京23区の場合は東京都)が課税しています。課税は、固定資産の価格から算定される税額になります。
課税対象となる土地は、田や畑、住宅地、工場が建てられている土地、駐車場、山林、原野、鉱泉地などを用途によって地目別に分類して、売買実例価格などを基礎に評価額を計算します。宅地の評価額は地価公示価格の7割が目安です。
家屋には、住宅、店舗、工場、倉庫などがあります。
償却資産は各種製造設備等の機械・装置・備品、車両・運搬具、ブルドーザーなどの土木建設車両、飛行機、船、医療機器などの事業用資産で減価償却の対象となる資産です。
固定資産税の目的
固定資産税は普通税と呼ばれ、税収の用途が定められていない税金です。徴収した市町村は、市民が利用する道路や学校、公園などのインフラ・公共施設を整備したり、介護・福祉などの行政サービスに使ったりしています。
固定資産税の支払い先
固定資産税を徴税するのは全国の市町村(基礎自治体)です。ただし、東京23区(特別区)のみは東京都が課税します。
固定資産税は1950年に行われた地方税制度の根本的改革によって創設された税制で、固定資産の保有と市町村が提供するサービスの応益原則に基づいて、資産価値に応じて所有者に課税する仕組みとなりました。どの市町村にとっても税源の偏りが少なく、市町村税としてふさわしい基幹税目とされています。
固定資産税の税率
固定資産税の計算式は次の通りです。
固定資産税額=課税標準額×税率(標準税率1.4%)
課税標準額は税額の計算の基礎となるもので、毎年1月1日の資産価格です。総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、各市町村長は各固定資産を評価し、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税台帳の価格を決めます。建物や土地の固定資産税評価額はすべて3年に1度見直しが行われます。
土地の場合、課税標準額は課税台帳に登録された土地価格をもとに、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用して算出されます。課税標準額が30万円未満の土地の場合、固定資産税はかかりません。
家屋の課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されている価格です。家屋は経年とともに評価額が下がります。用途などによって異なる所定の経過年数に達すると、再建築した場合の家屋の評価額である再建築費の2割になり、それ以後の評価額は一定になります。課税標準額が20万円未満の家屋には、固定資産税はかかりません。
償却資産の価格等は、取得価額をもとに取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価額が計算されます。申告及び調査に基づいて、償却資産課税台帳に登録されます。150万円未満の償却資産には課税されません。
課税標準額は基本的に固定資産税評価額のことですが、特例で減額されることもあります。固定資産税の標準税率は1.4%ですが、市町村は必要に応じて条例で異なる税率を定めることができます。
都市計画税とは

都市計画税とは、市町村が都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業の費用に充てる目的で課税します。課税の対象は原則として市街化区域内の土地・家屋で、都市計画税の税率は固定資産の評価額に対して上限が0.3%と定められています。税率は市町村の自主判断に委ねられていて、条例で異なる税率を設定する自治体もあります。
都市計画事業では、道路、都市高速鉄道、公園、墓園、水道、ガス供給施設、下水道など、土地区画整理事業は公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るための土地の区画形質の変更などの事業が行われます。
固定資産税の軽減措置
固定資産税・都市計画税には一定の条件を満たすことによって、軽減措置を受けられる場合があります。それぞれの軽減措置について説明します(適用期間は2024年3月31日まで)。
土地の軽減措置
住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)には、土地分の固定資産税と都市計画税の軽減措置が適用されます(住宅用地の課税標準の特例)。住宅が空き家でも原則的にはこの特例が適用されます。
ただし、「特定空き家」に指定され、「勧告」を受けた空き家が建っている土地は適用外となります。また、構造上住宅と認められない場合や、使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合、居住の用に供するための必要な管理が行われていない場合で今後居住の用に供される見込みがないと認められる場合は敷地が住宅用地と認定されない可能性があります。その際は、軽減措置が適用されません。
小規模住宅用地
住宅用地のうち200㎡以下の部分は「小規模住宅用地の特例」により、土地分の固定資産税と都市計画税の課税標準額が以下のように軽減されます。
固定資産税:課税標準額×1/6
都市計画税:課税標準額×1/3
アパートやマンションなどの賃貸住宅のオーナー様の場合、200㎡×戸数以下の部分が小規模住宅用地になります。例えば、所有するアパートの戸数が5戸の用地の場合、200㎡×5戸=1,000㎡までの小規模住宅用地に特例が適用されます。
一般住宅用地
住宅用地のうち200㎡を超え家屋の床面積の10倍までの部分は「一般住宅用地の特例」により、土地分の固定資産税と都市計画税の課税標準額が以下のように軽減されます。
固定資産税:課税標準額×1/3
都市計画税:課税標準額×2/3
例えば、面積が350㎡の住宅用地では、200㎡までの部分には小規模住宅用地の特例が適用され、200㎡を超える部分には、一般住宅用地の特例が適用されます。
住宅の軽減措置
住宅を新築した場合やリフォームした場合に、次のような軽減措置があります。
新築住宅
新築住宅については、1戸当たり居住部分に係る床面積で120㎡(120㎡を超えるものは120㎡相当分まで)の固定資産税額を限度に、家屋が竣工して初めて1月1日を迎えた年の4月から始まる年度、つまり固定資産税の課税開始年度から一定年度、建物にかかる固定資産税が1/2に減額されます。
減額期間は戸建ての一般住宅は3年間、3階建て以上の中高層耐火建築物(マンション)は5年間です。対象となる住宅は居住部分の割合が1/2以上で、居住部分の面積が50㎡以上280㎡以下、マンションの場合は40㎡以上280㎡以下です。
認定長期優良住宅

2009年6月4日より、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良住宅を認定する長期優良住宅認定制度が施行されました。
主な認定基準は以下の通りです。
- 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
- 耐震性:まれに発生する地震に対し継続利用のための改修の容易化を図るために損傷のレベルの低減を図ること
- 省エネルギー性:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
- 維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管の維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること
都道府県や市区町村等に認定された新築の長期優良住宅の場合、一般住宅に比べて固定資産税の減税期間がさらに長くなり、戸建て住宅5年、マンションは7年となります。対象床面積、減額割合は新築住宅と同じです。
バリアフリーリフォーム

築10年以上を経過した住宅に一定のバリアフリー改修工事を行うと、翌年度分の固定資産税が2/3に減額されます。改修工事完了日から3ヶ月以内に条例に基づき申告書を提出することが必要です。減額する年度は翌年度1年度分です。
適用されるバリアフリー改修工事の主な内容は以下の通りです。
- 介助用の車いすで移動できるように通路や出入口の幅を拡張
- 既存の階段を撤去して階段を新設あるいは既存の階段を改良して勾配を緩和
- 浴室の床面積の増加・浴槽を低いものに取り換え、固定式移乗台設置、踏み台設置、水洗器具の取り換え・設置
- 浴室・脱衣所・便所・その他居室・玄関及びこれらを結ぶ経路に手すり設置・段差解消・滑りにくい床材に取り換え
- 便所の改良工事(介助のための床面積の拡張、座便式便座への取り換えなど)
- 出入り口の改良工事(開戸の引戸や折戸への取り換え、開戸のドアノブのレバーハンドルへの取り換え、戸の開閉を容易にする器具の設置など)
主な適用要件は以下の通りです。
- 新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸を除く)
- バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上で280㎡以下
- 店舗等併用住宅は居住用床面積が1/2以上
- 65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者、障がい者のいずれかが居住する住宅の改修工事
- 補助金等を除いた対象工事の工事費用が税込50万円超
- 2024年3月31日までに工事完了
省エネリフォーム
2014年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額が2/3に減額されます。改修工事完了日から3ヶ月以内に条例に基づき申告書を提出することが必要です。減額する年度は翌年度1年度分です。
適用される省エネ改修工事の内容は以下の通りです。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床・天井・壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事・高効率給湯器の設置工事・太陽熱利用システムの設置工事
適用要件は以下の通りです。
- 省エネ改修後の床面積が50㎡以上で280㎡以下
- 店舗等併用住宅は居住用床面積が1/2以上
- 省エネ改修後の断熱改修部位が2016年省エネ基準に適合
- 対象工事の工事費用が税込60万円超(補助金等は含まない)
- 2024年3月31日までに工事完了
耐震リフォーム

1982年1月1日以前に建築された住宅を現行(1981年6月1日以降)の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が1/2に減額されます。耐震工事が完了した日から3ヶ月以内に条例に基づき申告書を提出することが必要です。減額する年度は翌年度1年度分です。
主な適用要件は以下の通りです。
- 耐震改修工事費が50万円超(補助金等は含まない)
- 1982年1月1日以前に建てられた家屋
- 店舗等併用住宅の場合、居住用床面積は1/2以上
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
- 2024年3月31日までに工事完了
長期優良住宅化リフォーム
1982年1月1日以前に建てられた住宅を現行(1981年6月1日以降)の耐震基準に適合する耐震改修工事、または2014年4月1日以前の家屋に窓の断熱改修工事を含む一定の省エネ改修工事を行って増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合、翌年度の固定資産税が1/3に減額されます。改修工事が完了した日から3ヶ月以内に条例に基づき申告書を提出することが必要です。減額する年度は翌年度1年度分です。
適用要件は以下の通りです。
- リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 店舗等併用住宅は居住用床面積が1/2以上
- 補助金額等を除いた工事費用が税込50万円を超える一定の耐震改良工事、または工事費用が税込60万円を超える一定の省エネ改修工事
- 2024年3月31日までに工事完了
- 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく改修工事
固定資産税の軽減措置の申告方法
固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けるには申告あるいは申請手続きが必要な場合があります。その手続きについて解説します。
軽減措置を受けるには申告が必要
新築長期優良住宅の減額措置や、各種リフォームをした場合に固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けるには、原則として自治体への申告が必要になります。申告期限は変更のあった翌年の1月31日です。なお、詳細は各自治体によって異なるので、各自治体の担当部署に確認してください。
土地の場合
住宅用地の場合は、土地や家屋の状況に変更があった場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要になります。
住宅の場合
新築住宅の固定資産税減額は、自治体によっては申告が不要で自治体が各種資料や家屋調査等で確認します。申告が必要な場合、各自治体指定の申告書を利用してください。
新築住宅が認定長期優良住宅の場合、申告が必要になります。新築された認定長期優良住宅に課せられる固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書の提出及び自治体が交付する認定通知書の写しの添付が必要です。
住宅の場合は「固定資産税減額申告書」を提出します。その他、認定長期優良住宅、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、耐震リフォーム、長期優良住宅化リフォームごとに必要書類がありますが、内容は自治体によって異なる場合があるので、不動産が所在する市町村に確認してください。
まとめ
マイホームを購入すると固定資産税・都市計画税の支払いが必要になりますが、軽減措置を利用すれば減額が可能になります。軽減措置を利用するには、工事内容や適用要件に適合している必要があります。詳細は自治体によって異なる場合があり、軽減措置を受けるには申告が必要です。
土地・中古住宅を購入した際には、不動産仲介会社に尋ねましょう。固定資産税に限らず不動産に関わる租税公課について、いろいろと教えてもらえます。できれば、税金に強い不動産仲介会社と出会いたいところです。
不動産仲介会社をお探しの方は、大手6社(小田急不動産・住友不動産ステップ・東急リバブル・野村不動産ソリューションズ・三井不動産リアルティ・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する不動産一括査定サイト「すまいValue」をぜひご利用ください。
「すまいValue」は、全国835店舗(※)に対応し、物件種別や地域を選ぶだけで最大6社に一括で無料査定を依頼できます。入力は約60秒、短時間で複数社の査定依頼でき、安心して売却を検討できます。年間6社合計の成約件数は11万件超と、高い実績を誇ります。
売却の成功には優れた仲介会社選びが重要です。ぜひ「すまいValue」でご相談ください。
※2025年4月10日時点(賃貸専門店舗を含む)

<監修者>
公認 不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
株式会社 髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社 アーキバンク 取締役。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、不動産ファンドのAM事業部マネージャーとして従事。現在は不動産コンサルティング会社を立ち上げ、投資家や事業法人に対して不動産コンサルティングを行いながら、建築・不動産の専門家で形成される株式会社アーキバンクの取締役として、業界において革新的なサービスを開発・提供している。
- ※本コンテンツは公開日時点での法制度に基づいて作成しています。
- ※実際の取引での法制度の適用可否については、税理士・税務署等にご確認のうえ判断してください。


該当の住所を選択してください
人気記事ランキング
不動産査定をする前の基礎知識

お手数ですが、通信環境の良い所で再度お試しください。
お客様がお選びいただいた地域は、すまいValue運営各社の営業エリア外となっております。
該当の住所を選択してください

























